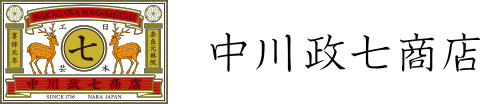現代のライフスタイルに即した新しい茶道の愉しみ方をご提案する、中川政七商店グループの新ブランド「茶論(さろん)」が月一回お届けする「宗慎茶ノ湯噺」。第六回のテーマは「七夕」です。
学び・習い事に縁の深い七夕
7月7日、空に横たわる天の川を探し、笹に願いの短冊を結ぶ。誰しも一度は経験するであろう夏の夜のたのしみ「七夕」は五節句のひとつ。もとは中国由来の風習です。
思い思いの願いが記される短冊。今では自由に、時に愉快な願いすら目にすることも多い短冊ですが、そもそも七夕で祈願されたのは、技芸や学問の上達でした。古くは陰暦7月7日に行われた七夕。今カレンダーに置き換えると、8月になります。お稽古事に勤しみ、何かを学ぶ人に縁深い歳事、今回は七夕のお話をしたいと思います。
平安貴族が欲した5つの“才(さえ)”
七夕の元になったのは「乞巧奠(きっこうでん)」と呼ばれる中国の行事です。
乞巧とは、牽牛・織女の二星に裁縫技術の上達を祈り、奠とは供物を捧げるの意。中国唐代では、庭に“乞巧楼”の櫓を設けて飾り立て、祈りを捧げたと言います。この星祭が、奈良時代に我が国にもたらされ、在来の棚機津女(たなばたつめ)の伝説や、祓(はら)えの神事と結びつき、やがて民間にも普及して現在も残る七夕となりました。日本における最初のを乞巧奠は755年御所の清涼殿庭で行われました。
はじめは女子が手芸や裁縫などの上達を祈った乞巧奠も、平安時代にはそ願いの幅が広げられ、男女を問わず、貴族たちが「和歌を上手に詠めますように」「字が上手になりますように」と自らの技芸の向上を祈る日に変化を遂げました。 光源氏や清少納言は何を祈ったのか。それは才(さえ)とも呼ばれたイケてる平安貴族に必須のスキルです。多くの古画に描かれ、物語の題材ともなった才。紐解いてみると今の人にも通じる点が多く、面白いものです。その中でも特に重宝された才を、いくつかご紹介します。
1. 外国語:漢籍詩文(かんせきしぶん) 漢文の読み書きができて、漢詩を作れる才です。 平安朝の宮廷では、公式文書は漢文で書かれていました。これが出来ないと「使えない…」と思われた訳です。 当時、近隣の大国であったのは中国。漢文のリテラシーがないと世界の最先端の知に直接触れることができませんでした。今風にいうと、外国語、特に英語が扱えるということでしょうか。バイリンガル、トリリンガルのバイタリティに溢れた幅広い視野を持った人材が評価を受けるのです。
2. 芸術:琴棋書画(きんきしょが) 琴、囲碁、書画が上手なこと、つまり芸術の才能を指します。 琴は音楽に通じていること。棋は、囲碁や将棋といったゲーム、娯楽といった趣味があるということ。書画は、“絵を描いたり書を書いたりできる”ということ。今風に言うと、アート・デザインに通じているといったニュアンスです。仕事ばかりでは駄目。余技、余芸に通じる、趣味も豊富で豊かな人柄がモテた、のです。
3. スポーツ:蹴鞠(けまり/しゅうきく) 平安貴族にもてはやされたスポーツは、まず第一に蹴鞠(けまり)です。よほどワイルドな人なら馬術。蹴鞠が上手になるように、との願いは、乞巧奠の代表的な願い事でした。インテリである上に、アウトドアやスポーツにコンシャスな男性が人気を博すことに時代の別は無いようです。
4. 医術:典薬(てんやく) 医学的な知識、健康管理に秀でてること。 どんなに技芸をたくさんに身につけて優秀でも、体を壊しがちで体力がないのは困るので、健康管理ができるというのは、大事なことです。メンタル、ボディ両面のヘルスケアが大切。
5.和歌:倭哥(やまとうた) 先に紹介した四つの才以上に、何より冴えてなければならなかったもの。それは和歌です。和歌のやりとりに秀でるとは、男女の色恋に通じているということ。そこには大きな意味合いが込められてます。他人の気持ちが分かる、人情の機微に通じている、人の痛みがわかること。けして恋愛ゲームの達人が求められた訳ではありません。要するに性別を超えて「リア充でなければ出世できない」のが平安貴族の現実でした。
如何でしょう。何とも身につまされる内容ではありますが、平安貴族がぐっと身近に感じられる「才」のエピソード。人の営みは今も昔も変わらず、小さなものから大きなものまで悲喜こもごも。皆さんは七夕に何を願いますか。
七夕と葉書
さて、七夕に縁の深いもののひとつに葉書があります。小さな紙片にメッセージをしたためた手紙。普段何気なく葉書とよんでいますが、その語源は昔、和歌や詩を書き記すのに、自然の葉を使っていた事に由来します。葉っぱに書くから葉書、というわけです。
七夕につきものは、梶の葉(かじのは)。この梶の葉は細かな毛に覆われていて、墨の文字が乗るのです。先に紹介した乞巧奠の折に、昔の人たちは夏を迎えて大きく育ったサトイモの葉に溜まった夜露を天の神から受けた水だと考え、それで墨を溶き、梶の葉に和歌を記して願い事をしたと言います。
文字を認めた梶の葉は、水を張った盥(たらい)に浮かべ、そこに夜空を映すように飾られました。和歌も文字も上手くなりますように、ひいては、誰かとの縁も紡がれますように。織女牽牛の二星に祈りを捧げた祈りは明快です。傍らには硯や筆、琴といった楽器に碁盤、五色の糸、といったそれぞれのモチーフとなるべき品々が飾られました。もちろん蹴鞠も。
今に残された書画や茶道具の中にも、梶の葉を多く見かけます。独特の姿をした梶の葉は、七夕を示す何よりの意匠として、書画に限らず、茶道具や着物に、広く用いられるようになりました。
七夕を“たなばた”と読む理由
七夕の訓読みは「たなばた」。考えてみればおかしな話です。本来であれば漢字の「七」や「夕」にそのような読みは備わっていません。中国から渡ってきた星まつり乞巧奠こと「七夕」は、はじめは「しちせき」と呼ばれていました。それがいつの頃からか「たなばた」と呼ばれるようになった。それは何故か。
乞巧奠の行事が日本人に取り込まれる過程で、我が国古来の棚機津女(たなばたつめ)の物語と出会い、合わされていったことにその理由があります。 織女も、棚機津女も、どちらも神様のために清らかな織物を、機(はた)を用いて織る女性のお話。『古事記』には神様のために衣を機織りする女性のお話が、『万葉集』には「たなばたつめ」の名そのものが登場します。
為我登 織女之 其屋戸尓 織白布 織弖兼鴨 あがためと たなばたつめの そのやどに おるしろたへは おりてけむかも 『万葉集 二〇一七』
今、手織りの機(はた)と聞いて誰もが思い起こすのは、テーブルもしくは棚状に仕立てた枠組に経糸(たていと)を掛け、杼(ひ)や筬(おさ)と呼ばれる舟形の器具で緯糸(よこいと)を打ち込むようにして通す高機(はた)であると思います。 この高機も、かつては大陸からもたらされた先端技術の一つでした。これを古代日本に伝えたのが秦氏(はたうじ)であると言われています。 テーブル、棚のような機だから“たなばた”。 機とは、すなわち秦。渡来系の氏族「秦氏」は、京都の街を最初に開い一族であるとの伝承も伝わります。所縁の社(やしろ)が今も太秦に残る蚕ノ社(かいこのやしろ)。ミステリアスな三ツ鳥居で有名な古社です。もちろん太秦の地名も秦氏ゆかり。
「きれいな織物を上手に織れますように」という願いを込めた行事である七夕(しちせき)は、古き所縁を以って「たなばた」と読むようになりました。
最後に、織姫と彦星の伝説に改めて触れておきましょう。古代中国の「牛郎織女(ぎゅうろうしょくじょ)」の伝説です。星空を支配する天帝の娘、織女(織姫)は機織の名手でした。彼女の織った布は雲錦と呼ばれ、色も柄も美しく、丈夫で着心地も軽い、素晴らしい仕上がりに。日々健気に仕事に没頭する、美しく成長した娘の姿を見て、天帝は素敵な男性を紹介したいと思い、牽牛(彦星)を引き合わせます。やがて結ばれた2人は、お互いに夢中になるあまり、果たして働かなくなってしまいました。怒った天帝は織姫と彦星を引き離し、年に1度、7月7日の夜にだけ天の川を渡って会う事を許しました。普段は渡ることのできない天の川に橋を渡すのは、鵲(かささぎ)の役目だそう。中国の古典では「烏鵲河を填めて橋を成し、織女を渡らしむ」(『白孔六帖』ー『淮南子』より引用か)とあり、日本には菅公こと菅原道真の歌に「彦星の行あいを待つかささぎの 渡せる橋を われにかさなむ」があります。中国では織姫が橋を渡ってくるのに対し、日本では逆に男性の彦星が。なんだか面白いです。因みにこの故事に倣って、宮中の階(きざはし)を「かささぎのはし」とも呼びます。
ここまで見てきたように、様々なエピソードや伝説、付随するモチーフがある七夕は、茶人にとってとても愉しい行事です。梶の葉、五色の糸、かささぎ…菓子の名、茶道具のデザインなど、様々な形で七夕を表現できますから、取り合わせの愉しみに満ち、編集力が試される機会でもあります。
茶論にお越しの方の中には、奈良・樫舎の美しい菓子「棚機津女」をお召し上がりになった方もいらっしゃるのではないのでしょうか。ちなみに長いものを糸に見立てて食べるといいので、おそうめんも七夕の時期には好まれる食材の1つです。
皆さんも是非、七夕にまつわる様々なモチーフを探して茶会をひらく際の趣向に取り入れてみてください。
2019-08-07
【宗慎茶ノ湯噺】其の六 葉月 七夕

木村宗慎(きむら・そうしん)
1976年愛媛県生まれ。茶道家。神戸大学卒業。少年期より茶道を学び、1997年に芳心会を設立。京都・東京で同会稽古場を主宰。その一方で、茶の湯を軸に執筆活動や各種媒体、展覧会などの監修も手がける。また国内外のクリエイターとのコラボレートも多く、様々な角度から茶道の理解と普及に努めている。 2014年から「青花の会」世話人を務め、工芸美術誌『工芸青花』(新潮社刊)の編集にも携わる。現在、同誌編集委員。著書『一日一菓』(新潮社刊)でグルマン世界料理本大賞 Pastry 部門グランプリを受賞のほか、日本博物館協会や中国・国立茶葉博物館などからも顕彰を受ける。他の著書に『利休入門』(新潮社)『茶の湯デザイン』『千利休の功罪。』(ともにCCCメディアハウス)など。日本ペンクラブ会員。日本食文化会議運営委員長。