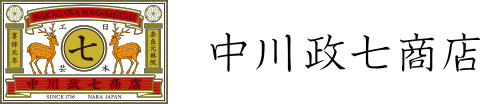ローカルファブリックLOCAL FABRIC産地をつないで紡ぐ、
着心地の良さを
追求した日常着
兵庫県神戸市を拠点に、日本各地の繊維産地に着目する繊維問屋「MILLE」が満を持して展開する生地ブランド「LOCAL FABRIC」。製織、染め、洗いなど、産地それぞれに息づく技の強みをかけ合わせ、繊維のもつポテンシャルを最大限に引き出しながら、着る人の「こうだったらいいのに」を叶える日常着を生み出す。
試した製品はタオルだけで1000種類以上、全国の産地を巡ってきた元商社マンの静かな革命
日本には多種多様な繊維産地がある。たとえば京都の丹後は絹織物の産地であり、福岡は久留米絣、岡山はデニムの産地として名を馳せる。産地それぞれに個性があり、得意とする技やノウハウもまた違う。昔ながらに受け継がれる伝統を守りながらその産地の中で生地をつくるのが多くの繊維産地の在り方だが、繊維問屋「MILLE」が展開するオリジナルブランド「LOCAL FABRIC」は一つの産地に留まることなく、異なる産地の強みや魅力をかけ合わせ、新しい生地や製品を生み出す。

仕入れて売るから〝一緒につくって一緒に売る〟へ
「ある意味、無謀な挑戦と言われれば、その通りなんですが……(笑)」
そう話すのはMILLE代表取締役の太田圭佑さん。かつて繊維専門商社に務め、タオルを中心とした商品企画に携わり、1000種類以上を試してきたプロである。

各地に息づく個性豊かな繊維を知り、多くのつくり手と接するうちに、ものづくりに対する姿勢や思いに深く共鳴した太田さんは「もっと、つくる側に寄った仕事がしたいと思ったんです。ただ仕入れて売るのではなく、一緒につくって一緒に売りたいという気持ちが高まった」と独立を決意。2021年に〝つくる〟から〝伝える〟までを担う繊維問屋MILLEを立ち上げた。
産地の強みをかけ合わせて〝欲しい〟をつくる
そもそも繊維製品はいくつもの工程を経てできている。糸を作る紡績をはじめ、糸や生地に色をつける染色、糸を織るまたは編んで生地にする織布・編立、できた生地の不純物などを取り除き、風合いをもたせる洗いや乾燥などの加工に至るまで。そのすべてを一貫生産するのが繊維産地の常道である。太田さんが「ある意味、無謀な挑戦……」と言っていたのはそのためで、ほかの産地と協力して一つの製品を作り上げることは型破りで難しいことだった。

太田さんを突き動かしたのは「もっとこうしたらいいのに」「こういう製品が欲しい」という消費者目線。そしてもう一つ、日本の繊維産業を守りたいという思いだ。海外製品の輸入などによって生産量が減少し、つくり手が減りつつある現状。それに伴い、「産地内で製造が完結できないという危機に直面する産地もあって……」。それらを解決するカギは「産地の強みをかけ合わせることにある」と異なる産地の“わざの連係”による生地づくりに乗り出した。
〝和歌山の吊り編み×愛媛の酵素洗い〟でつくる、分厚いのに柔らかく肌心地のいいTシャツ
LOCAL FABRICを代表する商品の一つがTシャツだ。私たちにとって馴染み深く着用頻度も高い製品ゆえに求められるハードルは高く、それを越えるための技術が必要になる。
「みなさんがTシャツに対して不満に思うことって何ですか? すぐにヨレる、透ける、分厚いと暑い、汗ではりつく、体型を拾う……そういった悩みを解消し、24時間でも着ていたくなるような肌心地を実現したのが、このTシャツです」と太田さん。

まず、タフな生地をつくるために選んだのは希少な旧式の“吊り編み機”。
吊り編みとは簡単に言えば、編機を上から吊り下げて、ゆっくりと回転させながら編むという独特な技法である。一般的な編み機なら1時間に7~8メートルの生地が編めるのに対して、こちらはわずか1メートル。生産効率は悪いものの、「糸に余計な力をかけずに編むことができるので、度を詰めた厚めの生地であっても、編み目にゆとりが生まれて空気を含んでいるような柔らかな質感になるんです」(太田さん)
そんな生地を用いてつくったTシャツに太田さんがかけ合わせたのは、今治タオルの産地、愛媛県西条市に位置する染工場「河上工芸所」が得意とする〝酵素洗い〟という強みである。

タオルは通常、織り上げた後に〝洗い〟という作業を行う。吸水性や通気性を高めるために、綿蝋(綿の糸に含まれる油分)や不純物などを取り除く工程である。
「一般的にはアルカリ剤などの化学薬品を使って処理するんですが、うちでは天然酵素を使った洗いを行います」と話すのは、取締役会長の三宅弘夫さん。20年以上前に酵素洗いの技術を開発した洗いのスペシャリストである。
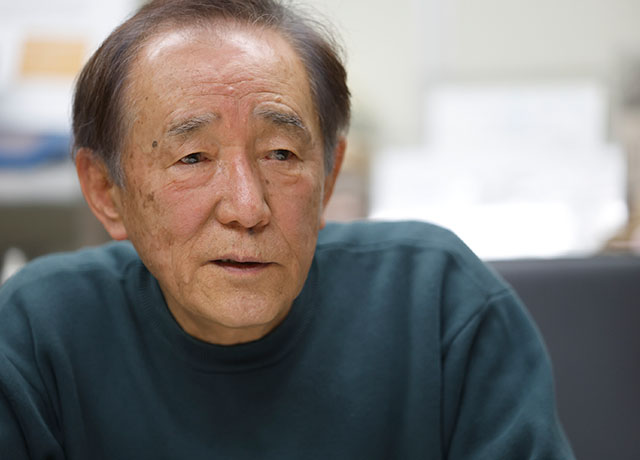

酵素洗いの最大の利点は「繊維を傷めないこと」と三宅さん。化学薬品を使うと汚れはきれいに落とすものの、どうしても糸が傷んでカサカサになる。それをカバーするために柔軟剤といった補剤が必要になるけれど、「酵素の場合は糸が傷つけられることなく、綿なら綿の、ウールならウールという繊維本来の柔らかさや弾力、風合いを活かすことができるんです」


素材や製品によって酵素の種類や使用数を変えるというが、LOCAL FABRICのTシャツに使うのは2種類。天然石鹸と石鎚山から湧き出る良質の天然水を使い、時間をかけて丁寧に洗いをかけることで、太田さんが求める「厚手なのに柔らかく、ベタつかず、ヨレにくいTシャツ」に仕上がるのだ。
〝兵庫の播州織×大阪の泉州タオル〟産地の技術連係でつくられた寝汗をしっかり吸う、やさしい風合いのパジャマ
シャツ生地の産地である兵庫県の“播州織”と、タオルの産地である大阪府の“泉州タオル”の強みのかけ合わせで作られたのが〝あんこ入りガーゼ〟というオリジナル生地のパジャマだ。
「あんこ入りガーゼは2層のガーゼ生地の間に束状のガーゼを打ち込んだ生地のこと。ガーゼ生地って薄いと頼りなく、厚いと手に余るじゃないですか。束状のガーゼ=あんこを入れることで安心感のあるボリュームをもたせることができるし、ガーゼ最大の特長である肌触りやふんわりとした軽さを維持することができるんです」と太田さん。


そして、パジャマといえば吸水性が肝になる。「寝ているとき、夏はもちろん冬でも汗をかくでしょう。汗を吸わなければ生地がベタッと張りついて気持ち悪いし、快適に過ごすことができない……大事なのは吸水性、吸水性といえばやっぱりタオルやな……(笑)」ということで訪れたのは日本タオルの発祥地、大阪・泉州。和泉山脈から流れ出る豊富な水源に恵まれた産地において、日本で最も多くのタオル加工を手がける染工場「ダイワタオル協同組合」に〝後晒し製法〟で仕上げてもらうことにした。


〝晒し〟とは綿に付着する糊や油分などの不純物を洗い落として漂白する作業のこと。織る前の糸の状態で行う先晒しに対し、後晒しは生地に織り上がった後の最終工程で行われる製法で、「先晒しよりも吸水性が高くなり、使いはじめから柔らかさを実感することができるんです」と工場長の神藤克人さん。特に同社は、アミラーゼという酵素の力を借りて、でんぷん質や不純物を分解する有機精練という技術を誇るのも強みである。


生地を乾燥させる方法にも一家言あり。同社は求められる仕上げによっていくつかの乾燥機を使い分けるが、あんこ入りガーゼには「ふわふわ感を活かすべく」タンブラー乾燥機を採用。「コインランドリーを連想してもらったら分かりやすいでしょうか。熱風を当てて空気を含むように乾燥させていきます」と神藤さん。


こうしてようやく出来上がったガーゼ生地はふわりと柔らかいことはもちろん、その吸水力の高さたるや!その違いは一目瞭然だ。
ちなみに泉州地区では、洗いに使用した水を高い基準を設けて濾過処理した上で排水している。「水の大切さを知っているからこそ、環境に徹底的に配慮したものづくりを行っていることも、この産地の強みだと思います」と太田さん。

少しずつ、でも確実に。LOCAL FABRICの未来を見据えた取り組みは日本各地にある繊維産地の壁を越えて、今もまた広がっている。
- 作り手情報
-
MILLE(ミル) 所在地:兵庫県神戸市
創業:令和3年(2021年)
公式HP:
https://mille-inc.com/
公式HP:
https://localfabric.jp/
4の商品
- カートに入りました
- カートを見る